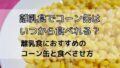離乳食でとうもろこしやコーンの缶詰を使う場合、薄皮を取るのが面倒ですよね。
赤ちゃんはまだ咀嚼力や消化器官が未熟なので、離乳食初期~中期まではとうもろこしは薄皮を取って与えます。
離乳食後期頃からは、少量であれば薄皮を取らずに小さく刻んで食べさせることができます。
離乳食でとうもろこしを食べさせるときに、ブレンダーやスプーンを使って簡単にとうもろこしの薄皮を取る方法をまとめました。
手作りの離乳食作りは大変ですよね。忙しいときには5秒でペースト状になる野菜フレークもおすすめです。
ブレンダーを使ったとうもろこしの薄皮の取り方
とうもろこしの薄皮がついたままでも、ブレンダーを使うと滑らかなペースト状にすることができます。
しかし、離乳初期ではブレンダーを使用しても必ず裏ごしをして、薄皮を取り除きます。
離乳中期でも、とうもろこしの薄皮は消化しにくいために下痢になることもあるので、裏ごしをしてきちんと薄皮を取り除いてあげてください。
手間はかかりますが、離乳食は赤ちゃんの大切な食事のスタートですので、手間を惜しまず一緒に食事を楽しむようになれればと思います。
忙しいお母さんは、余裕のある時にたくさん作り、製氷皿にわけ冷凍しておくと便利です。
茹でて薄皮を取り除いたとうもろこしは、そのままおかゆにかけたり、のばしてスープにしたりと、離乳食が進むにつれて調理方法も増えていきます。
ハンドブレンダーがあると離乳食だけでなく、いろいろな料理に使えて便利ですよね。
ブレンダーなしで簡単にとうもろこしの薄皮を取る方法
ブレンダーがないときは、スプーンを使っても簡単にとうもろこしの薄皮を取ることができます。
茹で上がったとうもろこしの表面1~2ミリ程度を包丁で薄く削るか、粒の表面に切れ込みを入れておきます。
そうすると、とうもろこしの粒の表面に穴が出来るので、スプーンで削り取ると実の中身だけ取り出す事が出来ます。
薄皮は芯についたままで剝がれません。
離乳食初期のとうもろこしの食べさせ方
離乳初期(5ヶ月~6ヶ月)の頃は、とうもろこしは茹でてからよくすり潰してから裏ごしして薄皮を取り除き、ペースト状にして与えます。
離乳食中期のとうもろこしの食べさせ方
離乳中期(7ヶ月~8ヶ月)の頃は、茹でたとうもろこしの実をそぎ落とし、みじん切りにして裏ごし器で薄皮を取り除きます。
離乳食後期~完了期では薄皮は取らなくてもいい?
離乳後期(9ヶ月~11ヶ月)頃から、少しの量なら薄皮がついていても食べられます。茹でたとうもろこしの実をそぎ落とし、細かく刻んで与えることができますが、裏ごしをした方が、栄養の吸収はよくなります。
離乳完了期(12ヶ月~18ヶ月)頃は、薄皮を取らなくても食べられますが、粒のまま一度に食べる量は小さじ1杯程度にします。
コーン缶の薄皮の取り方
手軽に使えるコーンの缶詰は離乳食には便利ですよね。
市販のコーンの缶詰の中には、砂糖や食塩が入っているものが多いので、離乳食に使うコーン缶を選ぶときは注意してくださいね。
いなば食品の「とれたてコーン食塩無添加」は、離乳食でも安心して使えます。
コーン缶を離乳食で使うときは、沸騰したお湯で軽く茹でてから、とうもろこしと同様にブレンダーを使ったり、すり鉢ですり潰してから裏ごしをして薄皮を取り除いてから赤ちゃんに与えます。
離乳食でコーン缶を使うときの注意点や食べさせ方は、こちらで詳しく紹介しています。

離乳食のとうもろこしの薄皮の取り方 まとめ
とうもろこしは甘いので、大好きな赤ちゃんも多いです。
とうもろこしの薄皮を取るのは大変ですが、ブレンダーと裏ごし器を使うと簡単に薄皮を取り除くことができます。
とうもろこしの薄皮は消化しにくく、下痢になってしまうこともあるので、離乳初期~中期までは必ず取るようにします。
栄養たっぷりのとうもろこしは赤ちゃんに食べさせたいけど、薄皮を取るのが面倒という場合は、5秒でペースト状になる野菜フレークもおすすめです。
少量づつ使えるので、赤ちゃんの離乳食作りには便利ですよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217807fa.96063f84.217807fb.7561d7ae/?me_id=1361741&item_id=10000127&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmama-select%2Fcabinet%2Fit%2F08000052%2F08378415%2Fimgrc0084534913.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[ポイント5倍!2/10(火)1時59分まで全品対象エントリー&購入]いなば食品 とれたてコーン食塩無添加 180g×3缶×8個入| 送料無料 スイートコーン 缶](https://i0.wp.com/thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/misonoya/cabinet/202306_01/r2_a464-16-1.jpg?resize=128%2C128&ssl=1)